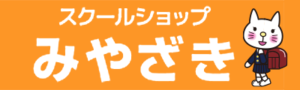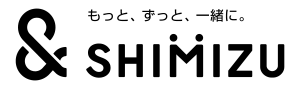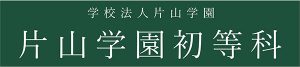Topics
編集部のライターたちが
富山での子育てに役立つ
付き添い入院を知っておこう

これからの季節は、インフルエンザや感染性胃腸炎など、子どもが病気にかかるリスクが高くなります。
大人なら数日で治るような症状も子どもは重症化することも。
入院となれば、親子ともに不安が大きいものです。
もしもの入院に備えて、事前に準備しておくことで、慌てることなく対応できます。
子どもの入院時の付き添いに必要な心構えと準備について子どもの入院経験のあるママライターが紹介します。
入院前の準備
○持ち物
・保険証またはマイナンバーカード
・母子手帳
・お薬手帳
・こども医療費受給資格証
・日常の薬(処方されている場合)
・着替え(多めにあるといい)
・タオル
・洗面道具
・シャンプーやボディーソープ(必要な場合)
・スプーンやフォーク、コップなど慣れた食器類
・ミルクやおむつ(乳幼児の場合)
・おもちゃや本(静かに遊べるもの)
病院によってはおもちゃや本が設置されていますが、
お気に入りを持参すると子どもの不安を和らげることができます。
入院はストレスを感じやすいため、好きな本やタブレットなど静かに時間を過ごせるアイテムを用意して気を紛らわせる工夫も役立ちます。
乳幼児の場合は、ミルクやおむつの準備が必須です。
私の子どもが生後3カ月で入院した時に、これらを事前に用意していなかったため、慌てて準備することになってしまいました。
子どもの病衣はない場合がほとんど。
熱があれば汗をかくことも多いので着替えはあって困ることはないです。
お気に入りのパジャマをお見舞いで買ってあげたら入院生活を少しは楽しく過ごせるかも。

子どものケアを第一に
年齢にもよりますが、子どもには入院の理由や手続きについて、説明するといいでしょう。
不安を取り除くために、入院予定の期間、治療内容、病院のことや医師、看護師の存在を話してあげることが大切です。
入院中の子どもにとって、親の存在は心強いものです。
できる限り一緒に過ごし、子どもが安心できる環境を作りましょう。
病院スタッフとの連携も大事
医師や看護師とのコミュニケーションを大切にし、わからないことや不安なことは積極的に質問しましょう。
アレルギーや病歴をまとめておくと、医師や看護師への説明がスムーズです。
顔色や呼吸の様子、うんちの回数や色など、なんだかいつもと違うという感覚はママにしかわからないこと。
シェアすることで治療に役立ったり、理由がわかり安心できたりします。
また、食事制限がなくても口にするものは、いつも食べている物でも看護師に確認してから食べさせましょう。
私の場合は、育児記録アプリを活用して、発熱の症状や解熱剤の投与時間などを記録していたので、医療スタッフに分かりやすく伝えることができました。
親自身のケア
付き添い入院は体力的にも精神的にも負担がかかります。
自分自身の体調管理を怠らず、無理をせずに休息を取るようにしましょう。
子どもの食事はありますが、親の分の食事はないことが基本。
私は事前に買い込んだインスタント麺を子どもが寝ている間に食べていました。
夫と交代したときに、自宅でお風呂に入ったり、ご飯を食べたりして乗り切りました。
また、入院ベッドは基本的に子ども用のもの一つしかなく、転落防止のために柵がついていました。
そのため、親はベッドの中で子どもと一緒に寝ることになり、寝返りがなかなか打てず体が痛くなることも。
付き添いをする際は、できるだけ楽な姿勢で休めるようにクッションやブランケットを活用すると良いでしょう。
入院となると子どものことばかりに気が入ってしまいますが、自身の準備をしっかりすることで子どものケアに集中できる環境づくりにつながります。
できるだけひとりで抱え込まずに家族で相談して協力して乗り切りましょう。
また、10日以上の付き添いが必要な方向けに、NPO法人キープ・ママ・スリングの「付き添い生活応援パック」というサポート制度もあります。
つきそい応援団というサイトから申し込むことができますよ。
○付き添いの持ち物
・着替え(楽な服装)
・洗面道具
・スキンケア用品
・飲み物や軽食
・寝具
・現金(自販機やコインランドリー用)
・洗濯用洗剤(必要な場合)

転落防止用の柵がついた子ども用ベッド
きょうだいのケア
きょうだいがいる場合、そのケアも重要になります。
私は上の子を義実家に預かってもらい、電話やビデオ通話でコミュニケーションをとるようにしましたが、やはり寂しさを感じる場面はあったようです。
事前にきょうだいにも入院のことを伝え、安心できる環境を作っておくことが大切だと感じました。
お手紙を書くのもオススメです。
一人で全てを抱え込まず、家族や友人、病院のサポートを積極的に活用しましょう。
日常のルーティーンについては、園生活は早朝保育や延長保育を活用するなどの対応が必要になる場合もあります。
利用が可能か園に相談してみましょう。
また、仲の良い友人がいたら保育園や学校の送迎は事情を説明して頼むことができると子どももお友達と過ごせて気持ちがまぎれるかもしれません。
他には、遠方に住むご両親にお願いしてきょうだいを迎えに行ってもらい、ご実家で預かってもらうという方法を取られる方もいました。
頼れる家族や友人が近くにいない場合、自治体のサポートサービスや病院の相談窓口を活用することができます。
事前に地域のサポート制度を調べておくと、いざというときに安心です。
もしもの備え
入院はある日突然やってくることがあります。
そのため、日頃からパートナーや親族と「もしもの場合」の想定をしておくことが大切です。
誰が付き添うのか、きょうだいの預け先はどうするか、必要な持ち物は何かを話し合っておくと、
実際に入院が必要になった際に慌てずに済みます。
私は、かかりつけの病院をリスト化し、保険証などをまとめたカバンを用意しています。
育児記録アプリを活用し、こまめに子どもの様子を記録しています。
退院後のフォローアップ
退院後の生活に必要なものを準備し、子どもの回復をサポートしましょう。
看護師や医師の指示があれば、食事や日常生活のリズムを整えることが大切です。
元気になったように見えても体力が落ちていたりメンタルが不安定になったりしているので
ゆっくりとペースを戻していきましょう。
定期的な通院やリハビリが必要な場合は、スケジュールをしっかりと管理し、忘れずに通院するようにしましょう。
私の子どもは酸素濃度が低下し、2回入院したので、酸素濃度を測定するパルスメーターを購入し、
体調を崩すたびに酸素濃度が下がっていないか気にするようにしています。
今回の入院を経験して、事前の準備や周囲のサポートがいかに大切かを実感しました。
自分の入院と、子どもの入院するのでは全く違う大変さがあることを痛感しました。
自分の入院であれば、体調管理や食事、休息を自分のペースで調整できますが、子どもの場合は常に付き添いが必要で、自分のことは後回しになりがちです。
私も最初は不安でしたが、周囲の助けを借りながら乗り越えることで、子どもも安心して過ごせたように思います。
入院は大変なことですが、少しでも負担を減らし、親子ともに乗り越えていけるようにしたいですね。
(ママライターS.E)